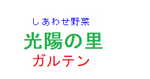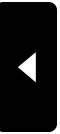2008年09月23日
オハギとアズキとマクロビオティック
 オハギとぼた餅の話に次いで、本日は小豆の話です。
オハギとぼた餅の話に次いで、本日は小豆の話です。お彼岸に「おはぎ」や「ぼたもち」を供えるのは、もともとは小豆の赤い色が災難から身を守り邪気を払うと信じられていたからです。
このことをマクロビオティック的に話をすると、「小豆はデトックス(排毒)の効果がある食べ物の代表です。」となります。
小豆に含まれているサポニンは利尿効果が高く、体のむくみを取り、体の中のをきれいにしてくれます。血栓(血の塊)を溶かす作用もあり、昔の人はお産の時にできた血栓が体の中を回って行って、心臓や脳で詰らないように産後には小豆粥を食べさせたそうです。
「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、当時は高価であった砂糖と一緒に小豆をいただくことで、疲れた体の中から毒を取り去りながら、新たなエネルギーを得ることができたのでしょうね。
小正月(1月15日)にアズキ粥を食べるのも同じ理由だと思います。
 アズキ 一口メモ
アズキ 一口メモ 
原産地はヒマラヤ山脈周辺と言われて、古くに日本に伝わり、登呂遺跡からも発見されています。
しかし、アメリカ大陸やヨーロッパでは今でも作られていません。
中国や朝鮮、日本など東アジア地域では栽培されていますが、アズキは日本人にだけ好まれる特異な存在のようで、赤飯やアンにして和菓子など広く使われていますが、中国のアンは緑豆を使うので小豆の栽培量は意外に少量で、日本での栽培量が最も多いそうです。
Posted by しあわせ野菜ガルテン at 20:00│Comments(0)
│6、花と自然の不思議、発見!