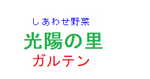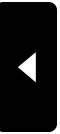› 光陽の里・しあわせ野菜ガルテン › 田打ち講
› 光陽の里・しあわせ野菜ガルテン › 田打ち講2009年01月11日
田打ち講
今日は1月11日、田打ち講(タブチコウ)の日です。

田打ち講は、日の出前に田んぼにススキを立てて新年の豊作をお願いする農家の行事で、家長と跡取りの長男だけで行います。
この田打ち講を最後にやったのは、もう30年以上前のこと、小さな時は寒くて嫌でしたが今となってとても大切な思い出です。
地域でも全く見られなくなってしまった田打ち講を、農業を始めたらまたやろうと以前から考えていたのですが、今日行うことができました。
 ススキ5本、萩を3本、これに縁起物の松竹梅を添えてから和紙を使った御幣(ごへい)を3個つけます。
ススキ5本、萩を3本、これに縁起物の松竹梅を添えてから和紙を使った御幣(ごへい)を3個つけます。
ススキはイネ科の植物でお米に見立てています。
萩は野の植物で、荒れ地を耕して田んぼにさせていただいたことへの感謝です。
家長と跡取りの数だけ作り供えます。父と子供なら2柱、孫がいれば3柱作ります。
写真に写っているのは父親です。少しは親孝行になったかなぁ。
 田を起こしてから太陽の方向(南)に向けて、しっかり立てます。
田を起こしてから太陽の方向(南)に向けて、しっかり立てます。
このままずっと立てておくのですが、倒れるとその年の稲が台風などで倒れてしまうとされています。倒れないようにしっかり耕します。
 最後にお正月の平餅を切って備えます。おせん米と言うそうです。お供え餅(丸餅)を供えるお宅もあるそうです。
最後にお正月の平餅を切って備えます。おせん米と言うそうです。お供え餅(丸餅)を供えるお宅もあるそうです。
準備ができたら祈りをします。。
 補足1
補足1
ススキを立てる前に田んぼを三本ぐわで立てる(耕す)のですが、この3本ぐわは年末にきれいに洗って、しめ縄をしておきます。田んぼの神様は鍬においでになるのです。
 補足2
補足2
今日は田打ち正月とも言います。正月ですから、夜明け前の田んぼで田打ち講をやって家に帰ってきたらお雑煮を食べます。
 補足3
補足3
今日のやり方は自分の両親から聞いたもので、正式かどうかはわかりません。
インターネットの情報も少なく、情報元も静岡県の西部地方のみです。
もしかしたらこの行事、この地域だけにあった貴重な文化なのかも知れません。
何か知っていることがありましたら教えてください。
田打ち講は、日の出前に田んぼにススキを立てて新年の豊作をお願いする農家の行事で、家長と跡取りの長男だけで行います。
この田打ち講を最後にやったのは、もう30年以上前のこと、小さな時は寒くて嫌でしたが今となってとても大切な思い出です。
地域でも全く見られなくなってしまった田打ち講を、農業を始めたらまたやろうと以前から考えていたのですが、今日行うことができました。
ススキはイネ科の植物でお米に見立てています。
萩は野の植物で、荒れ地を耕して田んぼにさせていただいたことへの感謝です。
家長と跡取りの数だけ作り供えます。父と子供なら2柱、孫がいれば3柱作ります。
写真に写っているのは父親です。少しは親孝行になったかなぁ。
このままずっと立てておくのですが、倒れるとその年の稲が台風などで倒れてしまうとされています。倒れないようにしっかり耕します。
準備ができたら祈りをします。。
 補足1
補足1ススキを立てる前に田んぼを三本ぐわで立てる(耕す)のですが、この3本ぐわは年末にきれいに洗って、しめ縄をしておきます。田んぼの神様は鍬においでになるのです。
 補足2
補足2今日は田打ち正月とも言います。正月ですから、夜明け前の田んぼで田打ち講をやって家に帰ってきたらお雑煮を食べます。
 補足3
補足3今日のやり方は自分の両親から聞いたもので、正式かどうかはわかりません。
インターネットの情報も少なく、情報元も静岡県の西部地方のみです。
もしかしたらこの行事、この地域だけにあった貴重な文化なのかも知れません。
何か知っていることがありましたら教えてください。
Posted by しあわせ野菜ガルテン at 20:21│Comments(0)